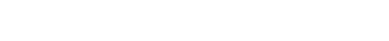6/18~20の二泊三日で、台湾のコーヒー農園に行ってきました。コーヒーの栽培風景を実際に見てみたいと思いつつも、ずっとチャンスがありませんでしたが、今回、日本国外ではおそらく一番近いオリジンであろう台湾のコーヒー農園に訪問することができました。台北や台中のコーヒーショップも訪れることができ、短い期間でしたが台湾のコーヒーシーンについて学ぶ素晴らしい機会でした。
この記事では、農園訪問前にStandart Japanのインスタグラムで集めた農園や台湾のコーヒーシーンに関する質問と回答をまとめてご紹介します。台湾のコーヒー栽培やコーヒーシーンについて気になっている方、行きたくても産地に行けないという方のために、少しでもこの情報が役立つと幸いです(質問と回答はインスタグラムのストーリーハイライト「台湾農園Trip」でも確認できます)。
コーヒー農園について
向かったのは台湾でも指折りのコーヒー農園、Fang Zheng Lun(方政倫)さんの Zhou Zhu Yuan(鄒築園)。下の写真が方政倫さんです。台湾ではCoffee Prince(珈琲王子)と呼ばれ、その知識や探究心、そして彼の作るコーヒーの質の高さから、台湾内だけでなく国外からも高く評価されています。コーヒー生産に関する教育にも力を入れていて、海外からもWBCなどの世界大会で使われる豆の生産を相談されるほど。
鄒築園は標高約1300mほどのところに位置する農園で、山岳部を開墾した農地にコーヒーが栽培されています。方政倫さんのご自宅(?)と併設されているカフェでは、方政倫さんの農園で取れたばかりのコーヒーを味わうことができます。

農園での日程ですが、まずはカフェでコーヒーを飲みながら、台湾のコーヒー生産についてのレクチャーと質疑応答からスタート。何種類ものデータや手書きのメモを見ながら、Fangさんがどのようにフレーバーを追求した科学的アプローチでコーヒーを栽培しているかや、農園の歴史について学びました。その後、カフェから車で3~4分ほど走ったところにある農園に移動して、急で細い山道を登りながらいくつかの栽培エリアを見せていただきました。レクチャーの内容を実際に目で見ながら再度確認できたため理解が深まりました。それから、精製処理施設へ移動して精製方法について伺った後、カッピングを行いました。どのコーヒーもフレーバーに特徴があり、紹興酒のようなフレーバーのゲシャ(ナチュラルプロセス)をテイスティングした瞬間の感動は、今もまだ強く印象に残っています。Fangさんの農園ではこのようなツアーに誰でも参加できるそうですよ。
インスタグラム Q&A
ここからは、インスタグラムのフォロワーの皆さんから集めた質問の回答をシェアしていきます。回答については、Standart Japan編集長のToshiが実際にFangさんや現地のコーヒー関係者から見聞きしたことをベースにお答えしています。あくまでひとつの農園からの情報となるため、この回答が絶対ではありません。ご理解ください。
質問1:栽培されている割合としては、アラビカ種とロブスタ種どちらが多いのでしょうか?
回答:アラビカ種です。そもそも台湾でコーヒーを栽培すること自体、コスト、生産量、環境などの側面から、大変難しいとのこと。手間がかかる分、コストもそれだけ上がっていくので、コーヒーで生計を立てていくには、ずば抜けた品質のものを作り、高くても買い手がつくものを精査しなければならないとFangさんはおっしゃっていました。だからこそ、今のところ選択肢がアラビカ種以外ないようです(例外はあるかと思います)。ただしFangさんはロブスタもきちんと手間をかけて育ててやればいいものができると考えていて、ロブスタの根にゲシャを接木して試験的に育てていました。また、Fangさんの農園では、ゲシャ、ティピカ、ブルボンなどの品種が主に栽培されています。

質問2:他の世界各地の農園と、どのように差別化しようとしているのか。
回答:科学的なアプローチを差別化の主要素として考えています。前述した台湾の栽培環境の制限から、フレーバーを突き詰めるために科学的なアプローチを取り入れているとのこと。他国では収量を増やすための研究は積極的に行われていますが、フレーバーをベースとした研究はまだ少ないとFangさんはおっしゃっていました。具体的には、土やコーヒーの葉の成分を分析して、月ごとの統計を取り、そこからコーヒーにとって何が足りないのかを判断します。そして分析結果をもとにコーヒーノキを剪定したり、有機肥料を使ったりして、コーヒーにとっての最適な環境を作り出すことに注力しています。
また、パナマや他の中南米から様々な種類の(様々な国で栽培されている)ゲシャの種を取り寄せ、台湾の気候に合ったものを探すということにも取り組んでいます。それぞれの特徴を記録したデータや成長の様子はWorld Coffee Researchに送られ、今後の台湾のコーヒー栽培や品種改良に活かされるそう。ここで育ったゲシャは毎年台湾を襲う台風や、Fangさんの農園の環境(高温多湿、冬の気温は0度ほどまで低下)に適応していくため、将来的に台湾の環境に適したゲシャが生まれるだろうと期待されています。

質問3:沖縄と同じく台風が多いイメージですが、どんな対策をされているのか知りたいです!
回答:次の写真のように、コーヒーノキ一本一本に鉄の棒をあてがって幹を補強しています。 地中1.5mほど埋まっていて、成長とともに長さを調整していきます。この対応をするのは6歳くらいまでの木で、それ以降になると幹もしっかりとして、台風にも自力で耐えれるようになるそうです。こういった対応をしているのは台湾のコーヒー農家の約6割程度で、他は運任せとのこと。管理や設備に相当手間や資金がかかるのは間違いなく、全ての農家が同じような対策を取れるわけではないのでしょう。

質問4:コーヒーと一緒に育てている果物はありますか?
回答:Fangさんの農園にはバナナが植えてありましたが、特に決まったものはなく、シェードツリーもないそうです。代わりに、コーヒーの木や葉っぱの水分量が不足しないように、定期的に水を撒くスプリンクラーが設置されていました。地上から2~2.5mくらいの位置に突き出した鉄の棒から、空中に向かって水を撒くようなものです。シェードツリーの役目は色々とありますが、木々を日光から守ることで乾燥を防ぐというのが主な目的だとFangさんは考えており、水分量を一定に保つことで同じ効果が得られると話してくれました。現に、Fangさんの農園のコーヒーノキはすべて青々とし、葉っぱは輝いており、見るからに元気そうでした。また、周りに植えられたものがコーヒーのフレーバーに影響することはないと考えているそうです。コーヒーが植えられている場所はFangさんのお父さんの代(世襲)ではお茶農園だったようですが、それもコーヒーの味に影響を与えることはない、とおっしゃっていました。成分などもチェックした結果で判断したようです。

質問5:台湾でのコーヒー農園経営は、金銭面的にいいビジネスですか?
回答:お金の話、気になりますよね。簡単ではないようです。先述した制約もあり、質の良いものを作っていく以外、生きる道がないとおっしゃっていました。台湾のコーヒーは高くて地元のコーヒーショップでは手が出せないほどだとFangさんは言います。その主な要因は人件費のようですが、人件費を削減するチャンスもなかなかないそうです。というのも、台湾のコーヒー生産量は少なすぎるため、中南米などで使われている精製処理機械や施設は台湾に導入できない場合が多いとのこと。メーカー側は輸出やサポートが大変で割に合わないと考えているそうなんです。なので台湾のコーヒー農家は、精製用の機械をDIYするしかないそうです(小型のものはありますが、オートメーションできるほどのものはない)。Fangさんも、パナマで見た乾燥機(以下の写真のドラム)を地元の鉄鋼業者に頼んで作ってもらったと言います。自動で乾燥ができて、データも残せるようにカスタマイズしたそうです。大変な発想力と行動力ですよね。

質問6:台湾コーヒーの精製方法にはどのようなものがあるのか気になります!
回答:台湾全体では他にもあるかもしれませんが、Fangさんの農園ではウォッシュト、ナチュラル、ハニーの3種類の方法でコーヒーを精製していました。ちなみに、すべての精製方法で上の写真のドラムを使用しています。台湾は雨が多いので、基本、天日干しは向いていません。また、Fangさんの考えでは、乾燥のプロセスは機械に任せた方が安定するということでした。他の農家も同様だそうです。現在は、豆の状態によって乾燥工程をパターン化して、最適なプロファイルを模索しているとのこと。ゆくゆくは自動化したいそうです(現在はまだ手でかき混ぜたりすることもあるとのこと)。また、近年世界中のコーヒー産地で流行っている嫌気性発酵(アナエロビック・ファーメンテーション)も、少量であればできるものの、安定供給はできず、大量に作ろうと思うと設備投資が必要になるので難しいとのこと。そもそもFangさんは、精製で豆本来の味わいを変えてしまうということに疑問を抱いてるようです。ウォッシュトはすっぴん、ハニーは薄化粧、ナチュラルはバッチリメイク、アナエロビックは超厚化粧、というFangさんの例えは言い得て妙だなと感じました。いろんな意見が農家さんによってあると思いますが!

質問7:気候、栽培管理、収穫、精製処理のなかで、品質の良いコーヒーを栽培するために重要なことを、その優先順位とあわせて知りたいです(ぜひ理由も聞きたいです)。
回答:これは直接質問したわけではないのですが、Fangさんとお話する中では栽培管理を一番重要視しているようでした。気候はすでにあるものなので、順応していく品種を探す、または工夫していくというところでしょう。精製は糖分をコントロールすることがすべてとおっしゃっていました。収穫の際に雨が降れば水分量が多いので乾燥で調整する必要があるし、収穫したコーヒーチェリーの状態をみて精製処理をウォッシュトにするのか、ナチュラルにするのか、ハニーにするのかを決めるとのこと。これもすべてどうやって糖分をコントロールするかということに繋がるそうです。このことから自ずとランキングは見えてきそうです。結局、いいものが育たなければいいものはできないということなのでしょう。さび病をはじめとするコーヒーノキの病気も台湾にはあるようですが、植物さえ元気な状態を常にキープしてやれば、病気にはかからないとおっしゃっていました。人間と同じですね。

その他のお話 1
「阿里山」は台湾のコーヒー産地としてよく知られていますが、ある特定の山のことだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は阿里山という山があるわけではなく、10以上の山々からなる国定公園が阿里山エリアと呼ばれているんです。台湾が日本統治下にあった頃、 嘉義県あたりで有名だったレッドオークが輸出用にたくさん伐採されていて、一節によると、そのきにシロアリが群がり、山の麓から山を見上げると白くうごめいているのが見え、皆「アリ、アリ」と言っていたことから、阿里山と呼ばれるようになったそうです。つまり「阿里」は当て字とのこと。
その他のお話 2
樹齢のお話。コーヒーノキにはいわゆる生産寿命があるというのを聞いたことがありましたが、Fangさん曰く、木は剪定さえしっかりしてやれば、歳をとればとるほどいい味をつけるとのこと。年を重ねるごとに根が地中へ伸びていき、その分多くの養分を吸収、蓄えることができるので、剪定後に残った枝葉にその養分を集中させると素晴らしい実ができるということでした。
根をどれだけ伸ばせるかは、植物の成長に大きく関わるそうです。Fangさんが最近ゲシャを植えたときには、まず地面を3mほど掘って石を取り除き、根を伸ばせるような環境を作ったそうです。その結果、通常収穫までに3年近くかかるところ、約1年で実をつけるまで急成長したそう。
その他のお話 3
Fangさんは、SCAA(米国スペシャルティコーヒー協会)が定めた基準・手順にのっとってコーヒーの評価を行うことができる、Qグレーダーです。農家の人間でコーヒーの評価が自分でできない場合は、品評会や販売を通じてしか自身の豆の品質を判断できないため、品質改善をスピーディに行うことができないとおっしゃっていました。だからこそ、FangさんはQグレーダーとなり、自身の豆を客観的に判断することで、生産状況や精製状況へのフィードバックを即座に行うことができるようにしたそうです。
最後に
Fangさん以外の農園に実際に足を運んだことがあるわけではないため細かな比較はできませんが、見聞きしたものも含めて唯一言えるのは、どの農家の方も自分で情報収集を行いトライ&エラーを繰り返して、自分の中の正解を探し続けているということです。そして彼らは自分の得た知識を惜しみなく提供してくれます。
Fangさんは探究心の塊のような方でした。コーヒー業界だけでなく様々な業界の方と接する中でよく感じることですが、この探究心こそが成功に必要な能力なのではないでしょうか。ここでいう成功とは、もちろん金銭的な意味にとどまりません。今回の農園訪問では、コーヒーそのもの以外にも、仕事や業界、家族や人生と向き合う姿勢を学んだ気がします。⠀
⠀
コーヒー雑誌を作る上で、またひとつ異なる視点を得ることができました。